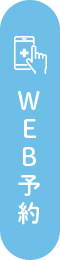胆石症 胆のうポリープ
- 2022年10月17日
- 胆のう病変
こんにちは。今回は胆石症、胆のうポリープといった胆のう内の病気についてです。
胆石症
胆石症とは胆道にできる結石の総称です。胆道とは肝臓でできた胆汁の通り道、つまり胆のうや胆管のことを指します。ただ結石は胆のうの中にできることがほとんどです。(以下、胆石症を胆のう内にある結石という意味で使用します)胆石をもつ方も食事の欧米化や高齢化によって増えてきております。最も胆石ができやすい方の特徴として「5F」が知られています。これは「Fatty(太った)」、「Female(女性)」、「Forty(40歳代)」、「Fair(白人)」、「Fecund(多産婦)」の頭文字をとったものになっています。
胆石症による特徴的な症状として右の肋骨の下の部分やみぞおちの痛み、右肩に放散する痛みがみられます。脂っこい食事をした後に出現することが多いです。(胆石発作)また胆石によって胆のうから胆管への交通がせき止められることにより、胆のう粘膜障害が起き細菌が繁殖して胆のう炎を来すこともあります。症状は発熱、腹痛(右肋骨下)です。さらには胆石が胆管の方へ落下して胆管に詰まって、十二指腸への胆汁流出が滞ることによっておこる胆管炎もあります。胆管炎の症状は発熱、腹痛、嘔気・嘔吐などがありますが、意識障害などを来すような重症になりやすい病態なので注意が必要です。無症状で経過することも2~3割あります。
胆石の症状を疑ったら検査を行いますが、画像的な診断となります。腹部超音波やCT、MRI検査などで描出されます。
胆石症の治療ですが、基本的には手術加療(胆のう摘出術)となります。胆石だけではなく、胆のうごととってしまいます。胆のうをとっても特に日常生活に支障は来しません。手術は胆石発作を繰り返す方や胆のう炎の方が適応となります。胆石をお持ちですが無症状の方は手術はせずに定期的な経過観察となります。
飲み薬(ウルソ)で結石を溶かすという方法もありますが、1年間しっかり薬をのんで30%程度の方しか効果がありません。また成功しても薬をやめると高頻度で再発してしまいますので、溶解後も薬を飲み続ける必要があります。
胆石症は肥満や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病と密につながっております。生活習慣を改善することが、胆石症の予防にも役立ちます。具体的にはまず過食・暴飲暴食を避けることが重要です。食事の面からはコレステロールの制限、脂質の適量摂取、蛋白質・食物繊維の摂取による便秘の予防、規則的な食生活、胃酸の過剰分泌を引き起こすアルコール飲料・香辛料などの過度の摂取の制限があげられます。
胆石を指摘されたことのない方は是非、生活習慣病にかからないような日常生活を送ってください。また指摘された方は経過観察が必要ですので、ご相談いただければと思います。
胆のうポリープ
胆のうポリープとは胆のうの壁から内側に向けて発生した隆起性病変のことを指します。
症状はありませんので、健診や人間ドックの超音波検査で偶然発見されることが多い疾患です。胆のうポリープの多くはコレステロールポリープという良性のものです。約90%を占めるとされています。その他、良性の過形成ポリープや、炎症性ポリープ、腺腫といった癌の前段階のポリープ、また胆のう癌そのものであることもあります。
治療としましてはやはり癌が疑われる病変が適応となってきます。評価する項目としましては①ポリープが10mm以上②経過観察中に大きくなってくる③大きさに関わらずポリープの茎が幅広いもの④超音波検査で癌が疑われる所見がある
治療は手術加療(胆のう摘出術)となります。
ただ小さいポリープであると上記のうちのどのポリープに当てはまるか見分けがつきません。だから大きくなってこないか、形が変わってこないかといったチェックが重要になってきます。目安として5mm以下では1年に1回程度、6~9mmでは半年に1回程度の腹部超音波検査での経過観察が推奨されています。
当院で超音波検査での経過観察も可能ですので、ご相談いただければと思います。
豊中市西緑丘3丁目14ー8
みやの消化器内科クリニック
院長 宮野 正人