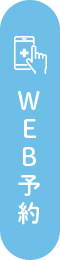低FODMAP食
こんにちは。今回は疾患ではありませんが、FODMAP食についてご説明します。
皆さん、下痢や便秘、腹部の膨満感、腹痛などの症状に悩まされていませんでしょうか。症状の程度は様々ですが多くの患者様がこれらのお腹の症状を自覚されると思います。これらの多くは過敏性腸症候群が原因となっていると思われます。
*過敏性腸症候群というのは大腸や小腸に明らかな異常がないにもかかわらず、下痢や便秘、腹痛、腹部膨満感などの症状があらわれる疾患です。機能性疾患のひとつであり、腸管の働きが乱れている状態です。原因としては身体的や精神的ストレスが大きく関与しています。
昨今注目されているFODMAPですが、これは小腸で吸収されにくい4種類の発酵性の糖質の頭文字をとったものです。これらの特定の糖質を過剰に摂取することによって、過敏性腸症候群を増悪させているということも言われております。このFODMAPの摂取を抑えた食事のことを低FODMAP食といいます。低FODMAP食は、特定の糖質の摂取を制限することで、主に過敏性腸症候群などの消化器症状(腹痛、ガス、膨満感、下痢や便秘など)を軽減することを目的とした食事療法です。
FODMAPとは次の糖質の頭文字をとったものです
| 略語 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| F | Fermentable(発酵性) | 腸内細菌によって発酵されやすい |
| O | Oligosaccharides(オリゴ糖) | フルクタン、ガラクトオリゴ糖(GOS)など |
| D | Disaccharides(二糖類) | 主にラクトース(乳糖) |
| M | Monosaccharides(単糖類) | フルクトース(果糖) |
| A | And | |
| P | Polyols(ポリオール) | ソルビトール、マンニトールなどの糖アルコール |
FODMAPは小腸で吸収されにくいため、過剰に摂取した場合は消化や吸収が追いつかず小腸内の糖質の濃度が上昇します。そうなるとそれを薄めるために水分を小腸内に引き寄せることで、便の水分量が多くなり下痢となります。また水分が多い小腸は、刺激に過剰反応するため、お腹が鳴ったり、腹痛を来すようになります。
小腸で消化・吸収できなかった糖質は大腸に到達し、腸内細菌による発酵でガスが発生 することでお腹の張りや痛み、ガス溜まり、便秘を引き起こします。
過敏性腸症候群をお持ちの方はこれらの作用に対して過敏に反応します。FODMAPの制限することによって症状が大幅に改善することがあります。
高FODMAP食品と低FODMAP食品の一覧
高FODMAP食品(一時的に避ける)
| カテゴリ | 食品例 |
|---|---|
| 野菜 | 玉ねぎ、にんにく、カリフラワー、マッシュルーム、アスパラガス、ブロッコリー、セロリ、キムチ |
| 果物 | りんご、梨、スイカ、マンゴー、さくらんぼ、ぶどう、アボカド、チェリー、もも、グレープフルーツ |
| 穀物 |
小麦、ライ麦、大麦、パン、ラーメン、パスタ、うどん、そうめん、とうもろこし、お好み焼き、ピザ、焼き菓子、パンケーキ |
| 乳製品 | 牛乳、ヨーグルト、チーズ(プロセス、ブルー、クリーム)、アイスクリーム、プリン |
| 豆類 | レンズ豆、ひよこ豆、黒豆、大豆(枝豆、納豆、豆乳など) |
| 甘味料・調味料 | はちみつ、フルクトース、ソルビトール、キシリトール、オリゴ糖、バルサミコ酢、ケチャップ、バーベキューソース |
低FODMAP食品(摂取OK)
| カテゴリ | 食品例 |
|---|---|
| 野菜 | にんじん、トマト、なす、ズッキーニ、きゅうり、かぼちゃ、ほうれん草、白菜、レタス、じゃがいも |
| 果物 | バナナ、いちご、ブルーベリー、キウイ、オレンジ、パイナップル、ぶどう、メロン |
| 穀物 | 白米、玄米、そば(10割)、オートミール、タピオカ |
| 乳製品 | アーモンドミルク、バター、マーガリン、チーズ(モッツァレラ、パルメザン、カマンベール、チェダー) |
| 肉・魚 | 肉全般、卵、魚全般、木綿豆腐 |
| 甘味料・調味料 | マヨネーズ、ソース、酢、砂糖、みそ、唐辛子、メープルシロップ、ココナッツオイル |
*あくまでも一例ですので、この他にもたくさんあります。詳しくはwebなどで検索ください。
FODMAP食の実践方法(3段階)
🔹 ステップ:除去期(2~6週間)
FODMAPが消化器症状に影響しているかどうかを確認する期間です。
できるだけすべての高FODMAP食品を排除し、過敏性腸症候群などの症状がどのくらい軽減するかを確認します。
お腹の調子がよくなれば、そのまま続けて次のステップへ進みます。変化がないようなら原因が別にあることも考えらえますので、中止してください。
完全に排除する期間は長くても6週間以内が推奨されます。
🔹 ステップ2:再導入期
この期間では特定のFODMAPがお腹の症状の原因かどうかを確認するために、少しずつFODMAPを再導入します。(徐々に制限を解除していきます)
高FODMAP食品を1種類ずつ少量から試して症状が再度出現した場合は、その食品が原因となっていることがわかります。また少しずつ量も増やして、許容範囲を確かめましょう。
こうして自分にとって「問題のあるFODMAP群」を特定します。
🔹 ステップ3:維持期(個別最適化)
最後は自分に合わないFODMAPだけを避け、可能な限り食の幅を広げ、長期的なバランスの取れた食事を目指します。
このように低FODMAP食を利用することで症状改善につながることもあります。とはいえ食事のメニューを考えたり、長期間にわたる治療ですので、厳密にするとなるとなかなか大変であり根気のいる作業となります。考えるのが大変な方は、低FODMAP食の適切な食事メニューがwebに載っているのでご参考ください。ここまで厳密にしなくていいという方には、何かよく食べる高FODMAPの食材を一旦中止して様子みるのもよいかもしれません。
過敏性腸症候群のお薬で効果がない場合やお薬に頼りたくない方などは、一度試していただく価値はある治療法と考えます。
豊中市西緑丘3丁目14ー8
みやの消化器内科クリニック
院長 宮野 正人