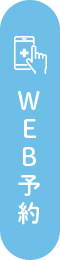カルチノイド(=神経内分泌腫瘍:NET)
こんにちは。今回は少し変わった比較的まれな腫瘍、カルチノイドについてご説明します。その中でも消化器領域では最も多い直腸カルチノイドを中心に説明しています。
カルチノイドの語源はカルチ:癌 ノイド:類 を表しており、意味としては「癌もどき」ということになります。癌と比べて比較的おとなしく、進行もゆっくりでありこのような命名をされておりましたが、実際には癌のようにリンパ節転移や遠隔転移を呈する症例もあります。だからカルチノイドを良性の腫瘍と誤った認識を防ぐために、2000年に世界保健機関(WHO)により神経内分泌腫瘍(neuroendocrine tumor:NET)という名称に変更されました。だから癌ではありませんが、進行性であり転移もあるので悪性腫瘍に分類される腫瘍です。( 以下より呼称をNETに統一します。)
このNETというのは文字通り神経内分泌細胞から発生する腫瘍です。神経内分泌細胞とはホルモンやペプチドなどを分泌する細胞の総称であり、全身に分布しているため、理論上はすべての臓器から発生し得ます。このうち消化器領域に発生するものが60%程度とされており、特に膵臓と直腸に発生するものが最も多いとされております。私としては実際は直腸NETは時々みられますが、膵NETは今までで1例しか経験したことはありません。
NETは腫瘍細胞の悪性度によって分かれ、「低~中悪性度」のNET G1,NET G2,NET G3と「高悪性度」のNEC(neuroendocrine carcinoma)に分類されます。この悪性度が上がることによりリンパ節転移や多臓器転移などの可能性も上がり、治療方法が変わってきます。
症状
症状としてはほとんどの場合は無症状です。ただ中にはホルモンを分泌するNET(機能性NET)が数%程度あり、そのホルモンにより顔面紅潮や下痢、腹痛、皮疹などを認めることがあります。
診断、検査
症状に乏しいので、直腸NETを見つけるには大腸内視鏡検査が必要です。内視鏡で直接観察し腫瘍の大きさ、場所、形や色調を確認した上で、NETが疑わしいとなれば生検による組織検査を行います。病理検査にて確定診断と悪性度を調べて治療方針を決定します。典型的な直腸NETの内視鏡像としては、表面が正常の粘膜の覆われた黄色調の隆起性病変です。癌や一般的な大腸ポリープとは違い、粘膜の深いところから発生するので、腫瘍によって下から粘膜表面が押し上げられるような形(粘膜下腫瘍の形態)をとります。通常の粘膜生検では腫瘍まで到達できない場合もありますので、その場合には診断をつけるために超音波内視鏡を使用して、腫瘍を確認しながら直接針を刺して組織を採取する方法もあります。また超音波内視鏡は腫瘍がどれくらいの深さまで浸潤しているかといった評価にも用いられます。転移の検索にはCT検査が有用です。
治療
治療法としては内視鏡的切除、外科的手術、薬物療法があり、腫瘍の悪性度や進行度によって方針を決定します。
・内視鏡的切除は腫瘍のサイズが1㎝以下の小さい腫瘍であり、形に不整な潰瘍や陥凹などがない場合に選択されます。超音波内視鏡やCTなどでリンパ節転移がないか確認した上で、治療を行います。方法はEMR(内視鏡的粘膜切除術)を応用した切除方法やESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)が行われます。
・腫瘍サイズが1㎝以上であったり、深部への浸潤やリンパ節転移が疑われる場合には手術療法が選択されます。手術で腫瘍ができている部位の腸管と共に周囲のリンパ節も切除してしまいます。NETの治療の原則は手術加療です。
・腫瘍が局所にとどまらず、他の臓器へ転移がある場合には、病状に合わせてホルモン療法、抗癌剤療法、放射線療法などを組み合わせて治療します。
基本的には治療方針はがんと同じです。内視鏡→手術→抗癌剤/放射線と腫瘍の進行具合により治療法は異なります。
当院で見つけたのはすべて直腸NETです。開院してからでいうと5例程度は見つかっております。大腸内視鏡時に偶然に発見されました。その場で生検検査を実施して、診断がつけば精査と治療目的で高次医療機関へご紹介させていただいております。
豊中市西緑丘3丁目14ー8
みやの消化器内科クリニック
院長 宮野 正人